2025.3.21
情報の透明性と信頼が循環を支える。社会性と経済合理性をつなぐバリューブックスの実践
利潤追求と環境保全や社会貢献を両立し、相互作用を生むビジネスはどのようなシステムのもとで実現されているのでしょうか。
今回お話をうかがったのは、書籍の買取・販売の事業を基盤としながら、本を起点としたさまざまなサービスを展開するバリューブックスの鳥居希さん。バリューブックスは、二次流通市場を有する点が自動車産業とも共通しています。インクルーシブかつ公平でリジェネラティブな経済システムをつくり出すグローバルムーブメントであり認証制度「B Corporation™︎ (B Corp)」の取得に尽力し、試行錯誤のなかにいる経営者からの“問いかけ”とは?

鳥居 希
1973年生まれ。長野県坂城町出身。慶應義塾大学文学部仏文学専攻卒業。モルガン・スタンレー証券(現モルガン・スタンレーMUFG証券)に15年間勤務。2015年、株式会社バリューブックス入社。B Corp認証取得を主導するとともに、『B Corpハンドブック よいビジネスの計測・実践・改善』を黒鳥社との共同プロジェクトによるコミュニティで翻訳。2022年6月、自社レーベル、バリューブックス・パブリッシング第1弾の書籍として出版する。2024年7月、同社代表取締役に就任。2024年3月、一般社団法人B Market Builder Japan設立、共同代表就任。
金融の世界を飛び出し、1人で起業する以上のインパクトを期待してバリューブックスへ
――まず、金融の世界で活躍されていた鳥居さんがバリューブックスに入社された経緯を教えてください。
私がバリューブックスに入社したのは、2015年7月です。もともと出身が、バリューブックスが拠点を置く長野県上田市の隣の坂城町なので、地元に戻ってきたということになります。大学卒業後に勤めたのは外資系証券会社でした。そこで15年、人々のビジネスに対するものすごいエネルギーを、社会をよくする方向にもっと生かすことができるのではないかと微かな想いを抱きつつも、やりがいを感じながら勤めていたのですが、ある日突然リストラを経験したんですね。
ちょうど雪の降った翌日のよく晴れた日で、空を見上げて「晴天の霹靂」とはこのことかと思った瞬間をはっきり覚えています。その後、別の会社で役員として1年働いたのですが、自分が思う仕事にはならず。もともと「いずれは地元で事業を始めよう」と思っていたので、もう先延ばしにすることはないなと、2014年に長野県に戻りました。
その時、幼馴染みだったバリューブックスの創業者・中村大樹と再会し、仕事の相談をしたり社員の人たちに会ったりするうちに、この人たちと一緒に仕事がしたいと思うようになったのです。

――前職とは大きなギャップがある印象を受けますが、バリューブックスのどこに関心を抱かれたのでしょうか。
創業者の言葉が胸に響きました。正確な表現は覚えていませんが、「本は自分たちが生まれるずっと前からあって、自分たちが死んでも残る。自分が生きているこの短い間に少しでも本と人との関係をよくしたい」という意味のことを語ったのです。失礼な言い方ですけど、こんな地方の中小企業がこれほど長い時間軸で考え、仕事をしていることに、ものすごく感銘を受けたんですね。
一方その頃には、「起業したい」と憧れる気持ちはあるものの、実際にやろうとしたら自分1人では何もできない、ということにも気づいていました。そして、なかなか成果を出せない事業を1人でやるより、この会社に入った方がよっぽどインパクトを出せるのではないかと思ったのです。
「嫌なこと」「困ること」を起点にすると社会課題とつながるビジネスになる
――古い本を買い取り、それを新たな読み手に届ける。価値を循環させるバリューブックスの事業とはどのような仕組みなのでしょうか。
現在、弊社の倉庫には常時約150万冊の本があり、それらを自社サイトやAmazon、楽天などのECサイトに流通させています。日々、全国から届く書籍をスタッフが1冊ずつ検品し、値付けをし、仕分けをして5つの倉庫に保管。ECサイトから注文が入ると、スタッフが倉庫の本棚から取り出し、ていねいに包装して発送するわけです。

バリューブックス上田原倉庫の様子
毎日、全国から届く古本は3万冊ほどですが、買い取ることができるのは約半分。本の状態がよくないもの、ISBNがないもの、ECサイトでの二次流通で値段のつかないものは買い取ることができず、それらは古紙として回収されます。買い取れない本の存在は、価値の循環を実現するうえで避けて通れない課題です。
その解決策の一つとして2018年に行ったのが送料の有料化でした。当初は予想通り一時的に利用者が減りましたが、工夫を重ね、今は理解を得られるようになってきました。利益を上げる体質にするのは簡単ではありません。いくつもの取り組みで徐々に利益体質に改善している状態です。
――バリューブックスでは書籍の買取・販売のみならず、さまざまなプロジェクトを展開されています。本を起点に広がったビジネスの変遷について教えていただけますか。
事業の拡充という側面よりは、社員がやりがいを感じられる機会の一つという側面が大きいですが、まず2009年に始めたのが、病院や学校など、本を必要としているけれど十分に揃えられない施設に無償で本を届けるプロジェクト「ブックギフト」です。
創業者の中村によれば、創業間もない当時、社員の退職理由はほとんどがライフステージの変化によるものだったそうです。ところがある時、初めて「社会との繋がりを感じられなかった」という理由で辞める人が出た。
今でこそ、カフェを併設した「本と茶 NABO(ネイボ)」や、値段がつかなかった古本を販売する「Valuebooks Lab.」など、利用者との交流の場をもっています。でも、当時はまだ会社の規模も小さく、ネットで買取の申し込みを受け、販売するという相手の顔が見えない仕事のみでした。こうした状況では、人にどう喜んでもらえているのかという実感が得られなかったのでしょう。

「本と茶 NABO(ネイボ)」
中村はそれを非常に重く捉え、社員のご家族のいるところ、保育園や学校、高齢者施設などにバリューブックスがプレゼントした本があれば、社員は誇りに思うのではないかと考えました。そして始めたのが、値段はつかないけれどきれいな状態の本を寄贈する「ブックギフト」でした。
ただ、ギフトは贈ることができる本の数も機会も限られます。もっと本業を生かして社会と価値を共有し、還元できるものはないかと考え、送ってくれた本の買取金額相当を、応援したい団体に寄付できる仕組みをスタートしました。これは今でも「チャリボン」として続き、今や支援先は大学やNPO、自治体などさまざまな団体に拡大しています。
2017年には、書店のない地域にも本を届けようと、移動式書店「ブックバス」の運営をスタートしました。
――社会性と経済性の融合については、どう折り合いをつけているのでしょう。
たとえば、2022年に始めたサービス「ブックプレゼント」は、本の買取金額の10%にあたる本を寄贈するプロジェクトです。これは、広告費用の一部を寄贈に使い、それを訴求することで買取を増やす取り組みで、いわばお金の使い方をシフトすることで社会性と経済性を両方とも実現しています。ただ、社会性と経済性の融合は、今後も課題として取り組んでいくことになるでしょう。
一方で、経済性とは別の観点でやらないといけないこともあると考えています。私が社長になることが決まってから、バリューブックスは役員会を刷新しました。めざしたのは、役員のメンバーを見た時に、社員の誰もがその中の少なくとも一人は自分とつながっている、もしくは自分のことをわかってくれている人が役員会にいると思えるメンバー構成にすること。ジェンダーギャップの解消も含め、一番身近なステークホルダーである社員に対する成果を、利益とは別の軸として置き、この役員会で取り組む重点テーマは「人」と決めています。
利益につなげていくものと、すぐには利益に結びつかないかもしれないけどやるべきことを分けて考える必要性については社内でも話題にあがります。経済合理性だけを追求しないという感覚は、役員だけではなく社員全員が根っこのところで共通して持っているのではないかと思いますね。
――バリューブックスの事業のなかには社会課題を意識されているものが少なくないように思えるのですが、そうした共通のカルチャーも影響しているのでしょうか。
どうでしょう。私たちは社会課題を解決するためにビジネスを作っているわけではありません。ただ、自分たちが嫌だと思うこと、困ることを解決していくと、それは社会課題とだいたいつながっていきます。
「ブックギフト」は、社員のやりがいを考えてスタートしたものですが、その背景には、古紙にせざるを得ない本の存在がありました。価値があると信じて送ってくれた本を古紙にすることが悲しくて、できるだけ本のまま活かそうと生み出した仕組みでもあったのです。古本を原料に利用して作った「本だったノート」「漫画だったノート」「雑誌だったノート」なども同様です。
困っていることを新たな価値にする仕組み作りを強化すれば、もっとやりたいことがきれいに回っていくのではないかと思うし、その可能性は十分あると思っています。

信頼を得るために必要なのは全体像を把握し情報を透明化すること
――本と自動車は、嗜好性の強い商材であり二次流通市場が存在する点が共通しています。二次流通市場というフィールドで「よいビジネス」をするために実践されてきたことがあれば教えてください。
情報の透明化が一つのカギになると思います。そのためには、バリューチェーンの上流から下流まで全体の現状を知ることが、大事なことだと考えています。
弊社では、2022年に自社の出版レーベルであるバリューブックス・パブリッシングを立ち上げました。もともと、流通市場の川下にいる私たちは、川上の部分、つまり本ができあがるところの流れは想像するしかありませんでしたが、本を作れば全体の流れが見えるようになるだろうと考えたのです。
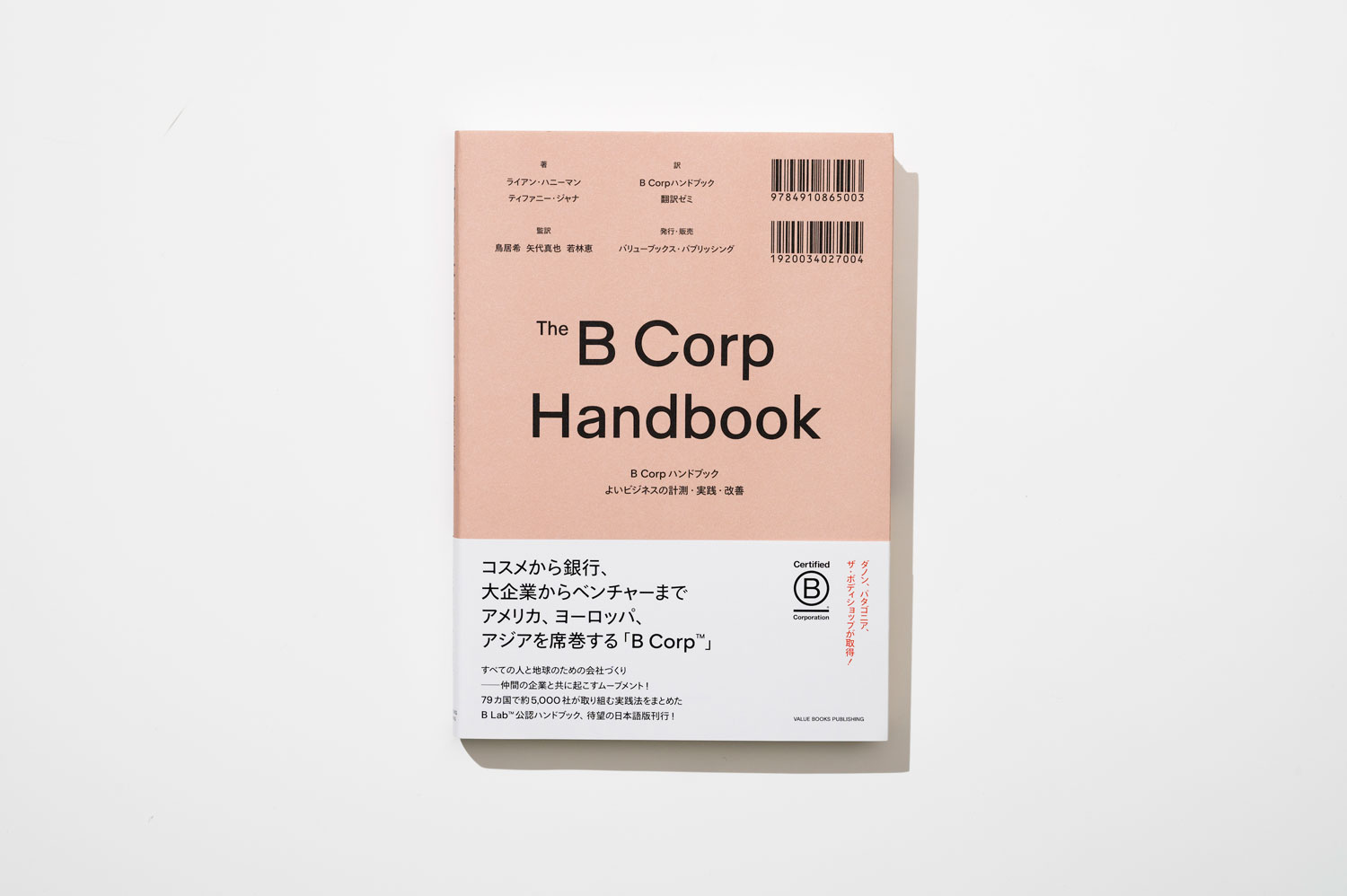
2022年にバリューブックス・パブリッシング刊行第一弾として『B Corpハンドブック よいビジネスの計測・実践・改善』を出版。そして2024年10月にバリューブックスはB Corp認証を取得。撮影:平松市聖(Ichisei Hiramatsu)
さらに、新刊の販売事業も手がけるようになり、本の作り手への還元率を上げるなど、自分たちに近いところにいるステークホルダーに利益をもたらすことで選んでもらえる仕組みを作りました。
買い取れない本を明らかにしたうえで送料を有料化したのも、経済性はもちろん信頼を得るための施策という側面があります。値段をつけなかったことを知らせることにはリスクもなくはありません。でも、それを知らせることの方が重要だと思うのです。
――経済性だけが理由ではないんですね。
さらに、コストの公平性という観点もあります。それまでは、ご自宅にある本を送っていただく際の送料を、弊社で負担していましたが、そうなると、弊社では買い取れない本もたくさん送られてきて、結果として多くが古紙に回ってしまっていました。利用者の地元で古紙回収に出せるはずのものが弊社に届くことで、無用な輸送費や人件費がかかり、買取金額を下げることにもつながってしまいます。
買い取ることができる本を送ってくれる人とそうでない人が同様にコストを負担するということは、結果的に不公平な事態を招いているわけです。その是正とロス削減のために、買取可能な本を明示し、その上で1箱500円の送料をいただき、その分、高い価格で買い取る仕組みに変更したということです。

バリューブックスでは上田市の郵便局と連携し配送の仕組みを独自に構築している
人に自由を与えエンパワーできるモビリティの力をもっとオープンに
――鳥居さんは国際認証「B Corp」取得に向けた取り組みを主導されました。認定基準は世界にいくつもありますが、なぜB Corpだったのでしょうか。
B Corpがいいと思ったのは、その基準が包括的で、もともと自分たちの価値観に近かったということと、認証を受けるだけでなく、ムーブメントの一部になれるということでした。自分たちだけでは成し遂げられないこともほかの企業の人たちと一緒であればできるかもしれないと考えています。
B Corpでは”Use business as a force for good -ビジネスをよりよい社会をつくるための力として使う”というフレーズをよく使います。それは、ビジネスを使って、次の世代に、より良い未来を残すこととも言えます。そう言った意味で、たとえば、台湾のB Corp企業が来日する際には、台湾と日本の歴史についての書籍リストを作って皆で共有するなどして勉強の機会を設けています。人と人が話すとき、本がよいクッションになってくれることが少なくありません。B Corp認定を取得した今、本を利用してほかの企業と進められることはたくさんあると考えています。
――自動車の研究開発のプロセスにおいて、日々どのような問いを立てることがよい研究、よい開発につながるとお考えですか? 鳥居さんの視点でヒントをいただければと思います。
私には、ある時から抱くようになった違和感があります。背の低い私は、運転の際にシートにクッションを敷くなどして座高を高くして視界を調整しています。それまでも、自分が基準に合わせて工夫するのは当然だと思っていました。ところが、B Corpについて勉強をしていくうちに、これはおかしくないかなと思い始めたのです。
マジョリティに合わせるためのコストをなぜ一部の人だけが払うのかと。性差についても同様で、たとえば男性基準でつくられたサービスやルールに合わせて、不便な部分のコストを女性が調整していることがあるかもしれません。
多様性がうたわれる時代ですし、コストをオープンにしてみんなで公平に負担するような計算が技術的にも可能なのではないでしょうか。エンジニアの方たちにも、そんな視点を持っていただけたらいいなと思います。

――そのほか、モビリティに対して期待することがあればお聞かせください。
私は長らくペーパードライバーで、長野に帰ってきてから運転を始めました。その時に感じたのが「自由になった!」ということ。それまではいつも誰かの車に乗せてもらっていたので、途中寄りたいところがあっても、自分のタイミングで立ち寄ることが簡単ではなかったんですね。
それが、行きたいところに自分のタイミングで行けるようになって、めちゃくちゃエンパワーされたと感じました。そんな利用者の視点もお伝えしておきたいと思います。
〈鳥居希さんからの問いかけ〉
不便さを解消するコストを公平に負担して、誰もがよいサービスを享受できるしくみを実現するために、あなたには何ができますか?
